この「場所」で生きているリアリティ。濃密な交流が生んだ復興支援プロジェクト
2024年1月1日に発災した令和6年能登半島地震で被災した「奥能登国際芸術祭」の復興を基軸に、芸術祭の枠を超えた復興に今もなお尽力されている「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」。「能登半島に寄せる奥能登珠洲ヤッサープロジェクトの想い」では、同芸術祭を通じてつながる人々の活動を通して、発災からこれまでの被災状況と災害が及ぼした影響を共有し、復興状況の今を紹介してきました。
最終回はプロジェクトの代表であり、芸術祭の総合ディレクターの北川フラムさんにインタビューをし、お話をうかがいました。また、ネットTAMで実施したアートマネジメントの連続ゼミナール「TAMスタジオ」の参加者であるスタジオメイトたちがインタビューに参加し、アートの現場視察番外編も実施。寄せてくださった所感を掲載しています。
2024年1月1日に起きた能登半島地震からの復興のため、「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」の立ち上げが決定したのは早くも同月4日のこと。「奥能登国際芸術祭の関係者やアーティストたちから、復興を支援したいという声が上がりました」と振り返るのは、奥能登国際芸術祭の総合ディレクター、そして奥能登珠洲ヤッサープロジェクトの代表を務める北川フラム氏だ。
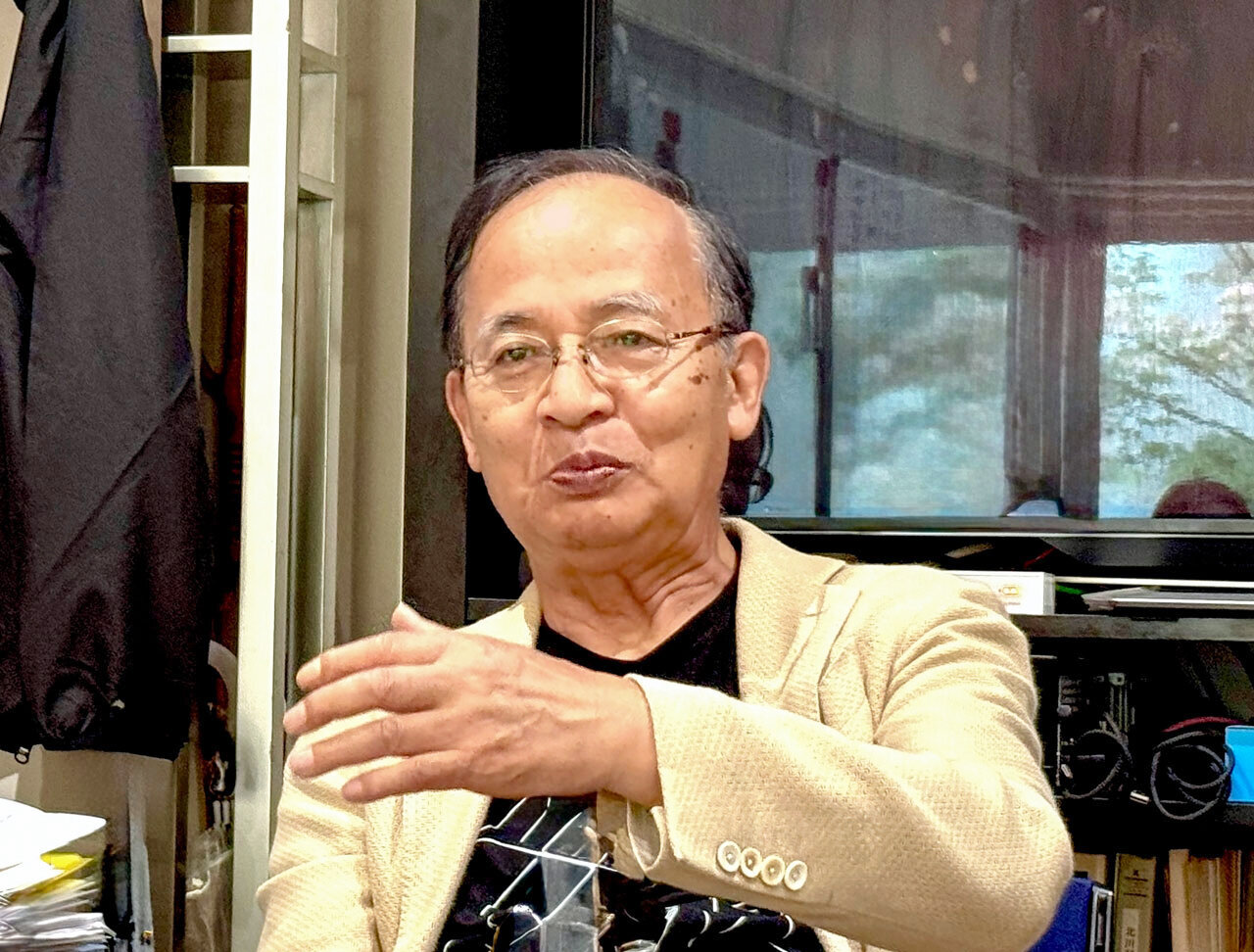
北川フラム氏
実際に出会った人が被災したという「リアリティ」
芸術祭で培ってきた人脈や経験を活かせることもあり、北川氏が率いる株式会社アートフロントギャラリーが中心となって、プロジェクトは始動した。事業内容には、被害を被った作品の修繕など芸術祭に直接かかわるものだけでなく、「震災のコミュニティ・アーカイブ」「復興ツアーの受け入れ」なども含まれている。支援の申し出は、芸術祭にかかわった人からのものが、圧倒的に多いという。
北川:やはり地域に対するリアリティの感じ方がまったく違うというのが芸術祭の特徴です。芸術祭では現場をたくさん歩きますね。そして地域のお年寄りや住民たちが対応してくれる、その密度がものすごい。今回被災した方々というのは、あの時の芸術祭で実際に出会ったお爺ちゃんお婆ちゃんだということに、故郷にも近いリアリティを皆さんが感じているのだと思います。

2024年3月スズシアターミュージアム外構
たしかに漠然とした「被災者」ではなく、具体的な顔を思い浮かべることのできる誰かのために協力したいと考える人は多いだろう。そして、芸術祭がきっかけになって、被災地支援が活発化した経験は北川氏にとってこれが初めてではない。やはり総合ディレクターを務め、いわゆる地域芸術祭のモデルとして位置づけられる「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」でも、2004年の中越地震からの復興に芸術祭が果たした役割は大きかったようだ。
北川:『大地の手伝い』と名づけて、アーティストや建築家を呼んで復興を手伝いました。アーティストは作品制作をしていないときは時間もあるし、お年寄りの話を焦らず聴くのが得意なんですね。建築家はもちろん解体作業ができるし。そうこうしていたら地元の人たちから『芸術祭やろうよ』って。以前は、現代アートは理解のできないものと敬遠されていたのが、そのころから雰囲気が変わり出しました。
1994年の「越後妻有アートネックレス整備構想」を前身に、2000年に第1回が開催された大地の芸術祭は、当初は批判的な意見も多く「バスは空気を運んでいるだけ」と揶揄されることもあったというが、今では海外からも数多くの人が訪れ、2024年はバスツアーの売り上げだけでも1億5千万円になるという。「アートによる地域づくり」などと言葉でいえばたやすいことだが、長い年月をかけてそれを実証してきたといえよう。その手応えがあったからこそ、今回もいち早くヤッサープロジェクトの立ち上げを決意できたのだろう。
北川:芸術祭で感じるリアリティというのはアーティストにとっても楽しいものなんです。たとえばクリスチャン・ボルタンスキーみたいな世界的なアーティストでも、地域のお婆さんたちと普通に交流していて。やっぱりそういうリアルなコミュニケーションがうれしいんですよね。
そのようなリアリティのある濃密な交流の生まれる芸術祭だからこそ、数年に1回しか直接触れ合うことはなくとも強力なネットワークが築き上げられる。多くの芸術祭で取り入れられているサポーター制度の参加者についても、「知らない人同士の同窓会」のような関係になっていると北川氏は話す。ヤッサープロジェクトでも、まさにそのような遠くにありながらも緊密なネットワークが育まれている。
協働:北川フラム氏の一貫した姿勢
とはいえ、もちろん芸術祭をただ開催すれば自然にネットワークが構築されるわけではないだろう。週に5日は東京からの始発と最終で色々な地域を飛び回っているという北川氏自身の、誰よりも率先して動こうとする態度が周囲にも浸透して強力なエネルギーを生んでいるように感じる。ユネスコ(在パリ)の要請により日本開催の窓口となり1988年からの2年間、全国200カ所近くの会場を特製のトラックで巡回した「アパルトヘイト否(ノン)!国際美術展」は、まさに北川氏のエネルギーが全国の賛同者をネットワーク化したプロジェクトだったろう。そのような協働のかたちはどのようにして生まれるのか。
北川:協働というのは単純な話で、基本的に色々な人とのかかわり合いのなかでやっていかないとできないし、おもしろくない。それから最近になってわかったことですが、大乗仏教の教えに通じるところがあると思います。世界と自分とは反応し合うということです。自分は大切だけど、家族や知り合いも大切。今だったら、大変な目にあっているガザのことも同じように大事。それは人間の本能のようなものでしょう。それがずっとベースにあります。

アパルトヘイト否! 国際美術展 (公民館、体育館、文化センターなど会場も様々、全国を巡回した)
だからこそ、南アフリカ共和国の人種差別的なアパルトヘイトに反対する芸術展の開催が国際的に呼びかけられたとき、日本の多くの団体が実現の難しさを理由に尻込みするなか、北川氏は意を決して開催に踏み切ったのだろう。苦しんでいる人の助けになることをするという大乗仏教的な考え方は、今回のヤッサープロジェクトなどの災害復興プロジェクトをはじめ、北川氏のキャリアに一貫して読み取れる。高校生で新潟地震を体験し、阪神淡路大震災でも復興プロジェクトにかかわってきた北川氏だが、2011年の東日本大震災では「日本の骨格がぐにゃっと曲がった」ような印象を受けたという。
北川:今は日本という国全体が相当に弱っていると感じます。道路の陥没や列車の事故など、普通のことが普通にできない国になってしまった。こんなに落ち続けていて、未来に対しても何の展望もない。思い返せば、ジャパンアズナンバーワンとかいって、目くらましをされてきた数十年だった。自殺率も高く、日本の都市にはもう具体的なコミュニティが存在しない、もうだめだという感覚が以前からありました。田舎のコミュニティから始めるしかないと考えたことが、大地の芸術祭にもつながっていきます。
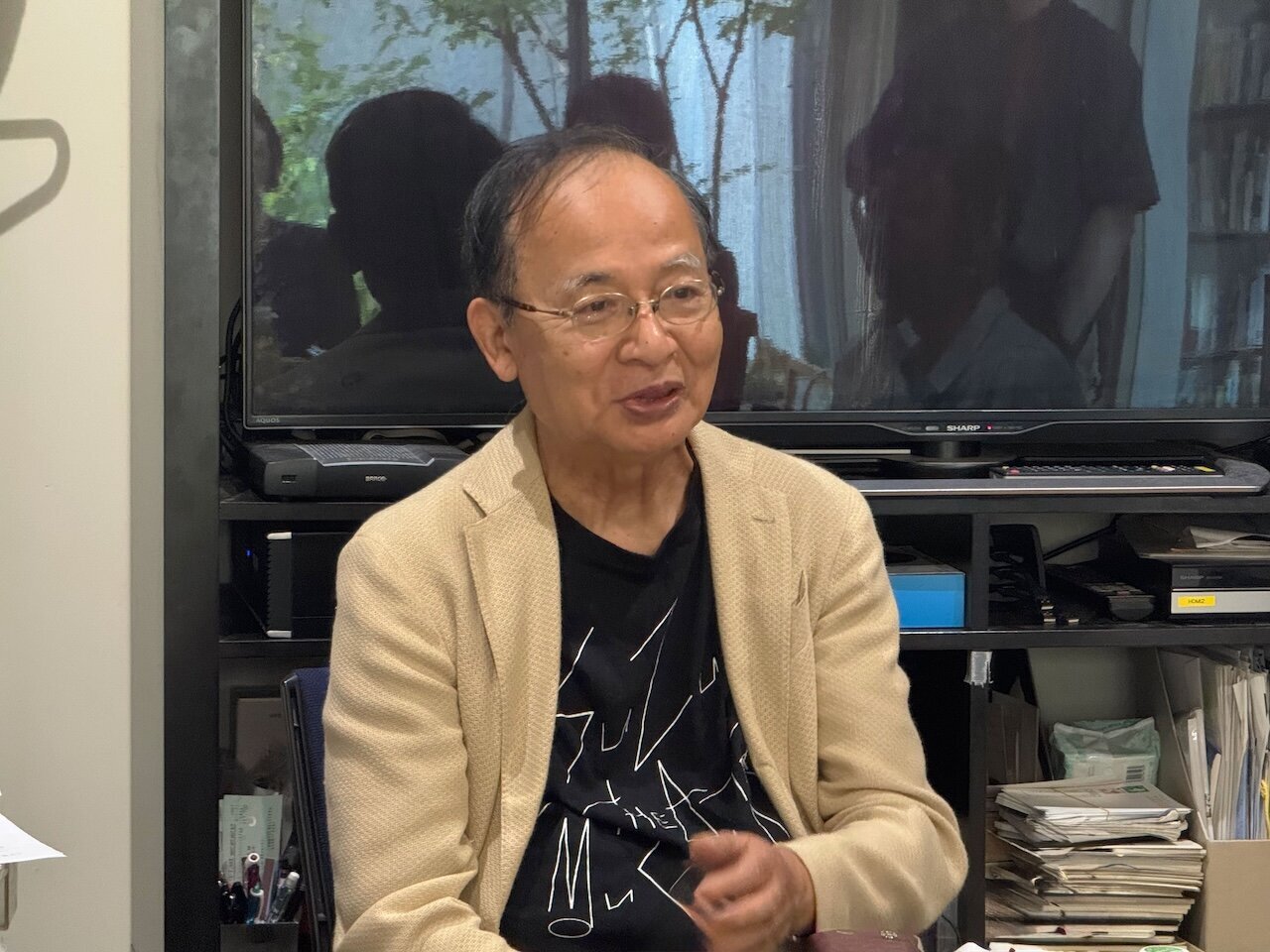
「絵が好きで美大に入ったけど、現実とまったく関係ないように動いていく美術」に違和感を覚えて、壁画のプロジェクトや、全国をトラックで巡回する「アパルトヘイト否(ノン)!国際美術展」、ファーレ立川のパブリックアート、そして地域型の芸術祭など、美術館やギャラリーのような空間を離れたプロジェクトをいくつも手がけてきた北川氏。「一つにはホワイトキューブの問題がある」と指摘する。
20世紀の理念「均質空間」がもたらす弊害
鉄筋コンクリート造にガラスのカーテンウォール、真っ白な壁で構成される抽象的で均質な展示空間は、効率性を重視する「20世紀の理念に適っている」としつつも、ホワイトキューブに代表される「均質空間というものが、現代の私たちを規定している一番の思想」だとして、北川氏は警鐘を鳴らす。
北川:均質空間の意義はいまだにあるし、これはこれで一つのすばらしい理念。でも今はそれどころじゃないでしょうという現実になってしまっています。顔を合わせても挨拶をしない、電車に乗れば足を蹴飛ばされる、そんな状況で、所属する自治体名をいっても意味がないほどに、この場所で生きているという感覚が失われています。
つるつるとして清潔な均質空間は、誰もがコミュニケーションのコストを払うことなしに効率よく便利な生活を享受できるものとして、なるほど「20世紀の理念」には合致していたのだろう。しかし、その結果として現在社会に蔓延しているのが、本来であれば面倒であっても協働し合う関係を築くべき相手を、具体的な顔を持たない存在としてみなしてしまう態度だとしたらどうだろう。その均質空間の傾向はインターネットの普及によりますます顕著になっているようだ。
北川:ウェブ社会では、情報が何となく頭に入ってきていてもお腹に入っている感覚がないですよね。昔は空の高さや海の深さにたとえられていた愛情も今は半角サイズ。記号の繰り返しに過ぎないものになっていると感じます。そんな時代でも美術にはまだ少しはできることがあると思います。美術というのは、昔から人間と自然や社会の一番の接触面にあるもの。頭の中で考えているだけでなく手触りとか、五感全部を使って思想をつくり上げるものです。

インタビューの様子
この日のインタビューでは、ネットTAMが開催する学生向けのアートマネジメントプログラム「TAMスタジオ」の、参加を希望する過去の参加者も同席し、北川氏に質問をする機会が設けられた。この春から新社会人として地域の文化施設に勤めている参加者には、「何事も好奇心を持ってやること。その場所がおもしろいと思ってやるしかない」というアドバイスが北川氏から贈られた。大地の芸術祭など数多くの芸術祭を抱えて手一杯だったにもかかわらず、奥能登国際芸術祭の開催を決めたのには「町並みがよかった」という理由がある。
北川:金沢に行ったついでに奥能登エリアを車で走っていて、夜でも町並みがよいんですね。町並みがよいというのは、たとえば日本でいえば広島を走っていて気になる教会があって調べてみると村野藤吾先生の作品だったり、フランスからドイツに向かっているときにもエッフェルの設計した駅に出合ったり、そういうことです。

熱心に耳を傾けるTAMスタジオ参加者スタジオメイトの皆さん
「その場所をおもしろがる」という助言や、このエピソードからは、雑誌『住宅建築』での北川氏による連載「断層の空間」を思い起こさせる。特定の場所や写真にじっくりと対峙し、手触りとともに考え続けるような北川氏の文章は、ある種の場所論として読むことも可能だろう。均質空間が失わせてきた「場所」の感覚やコミュニティが持つリアリティに触れ直すことから協働の精神を育むこと。奥能登国際芸術祭やヤッサープロジェクトで今起こっていることは、そのように表現できるかもしれない。

インタビューの様子
TAMスタジオ「アートの現場視察レポート」番外編
スタジオメイトの声
大変興味深いお話を聞けた有意義な時間でした。北川さんの実際のご経験に基づいて、さまざまな事例をふまえながら、お話してくださったので、非常にわかりやすく、参考になりました。特に、いくつかの震災を巡る話題は、文化芸術の範疇を超えて、現在を生きるうえで重要な視座を提示してくださったように思えます。短い時間ながら、多岐にわたる話題が展開されたので、私自身よりいっそう勉強を積みかさね、じっくり思考していきたいと考えております。
阿部優哉(武蔵大学人文科学研究科)
北川フラムさんのお話をうかがって、最も印象的だったのは芸術祭をプロデュースするうえで『アート』と同じくらい『地域』にも重きを置かれているということです。西洋的かつ画一的であるホワイトキューブという均質空間(もちろん、均質空間であるからこそ発揮されるポジティブな効果もあるが。)ではなく、鑑賞者が実際にまち、そして場所や時期に応じて日々移ろいゆく自然の中を歩きながらアート作品に触れられる仕組みを生み出す北川さんが、実際に何度もご自身で地域に足を運ばれてから芸術祭を構想されるとうかがい、その北川さんのフットワークの軽さと地域に対する想いに感銘を受けました。
また、芸術祭やそれに関するさまざまなイベント、継続的なコミュニティが形成されることは、北川さんが仰るように、アートが方法によれば公民館や保健所の役割を果たせる可能性があるということが非常に興味深かったです。比較的重視されにくい各地域における小規模なコミュニティ・つながりをアートが形成・持続する役割を担い得ると強く意識できた経験は、今回インタビューに参加させていただいて個人的に大きな意味があったように感じます。
このように貴重な機会を提供してくださったネットTAMのみなさま、そしてインタビュー会への参加を許可してくださった北川フラム様とアートフロントギャラリーのみなさまに心から感謝申し上げます。桂波那(四国学院大学)
"美術は来てくれるところから始められる"という北川フラムさんの言葉に芸術祭をやる意義を感じました。「来てくれる」ということに対し、まず「行く」こともハードルはありますが、"行けばおもしろい"と人から認識してもらえてるからこそ、芸術祭が成り立っているのだと思いました。
旅行などである場所に行って、観光することや暮らすこと、そこに住む人と時間を過ごすことなど、「行く」ことで体験できることは、土地によってたくさんあると思います。人がその土地に惹かれる理由もさまざまなため、芸術祭は「楽しそう、おもしろそう、行ってみたい」と思われる体験の一つであり、その場所に誘うことのできるきっかけになるのだと、お話からそう思いました。
美術だけでなく、その土地の力、住んでいる人、来てくれる人がいるから、「その場所で美術ができている」ということを忘れないよう心がけることや、「行ってみたい」と思ってもらえるよう働きかけることを、どうしたら実現できるかなど、今後も学び、考え続けたいと思います。金坂泉(株式会社KURKKU FIELDS)
インタビューでは、北川フラムさんが実際に現地を見ること、「リアリティ」を大切にされていることが印象的でした。私自身も、昨年初めて大地の芸術祭に訪れ、書籍やネットの情報では、自分の目で見て、自分の足で歩いて得た情報と全く違うということを実感しました。
頂いた質問の時間では、北川フラムさんに地域の方との関わり方や地域のニーズを見つける方法について尋ねたところ、ただ方法論を言うというのは簡単だけれど、まずやる・手を動かすしかないこと、地域を面白がること、という回答をいただきました。私は、4月から公民館の職員として働いています。地域と密接に関わるという点では、公民館での仕事も北川フラムさんのこれまでのお仕事と共通しており、何よりも地域について知ることの重要性を感じました。私が勤務する公民館のまわりだけでもまだまだ知らない場所があり、通ったことのない道があるので、地域や公民館という場所や利用者・地域の人々を面白がって見てみる・話してみることを大事にしたいと思いました。中村ゆかり(千葉市教育振興財団)
取材概要
- 取材日:2025年7月14日(月)
- 会場:アートフロントギャラリー
- 取材先:奥能登珠洲ヤッサープロジェクト 代表 北川フラムさん
- 取材者(文・構成):清水康介
- 取材参加者:TAMスタジオ2024・スタジオメイト(阿部優哉、桂波那、金坂泉、中村ゆかり)
- 写真撮影:ネットTAM運営事務局

取材者:清水康介(ライター)
主に文化や芸術に関わる分野で取材・執筆をしています。ウェブサイトの制作を請け負うこともあります。出身は関西ですが、2020年から長野県の松本市に住んでいます。仕事用のメールアドレスは
です。










